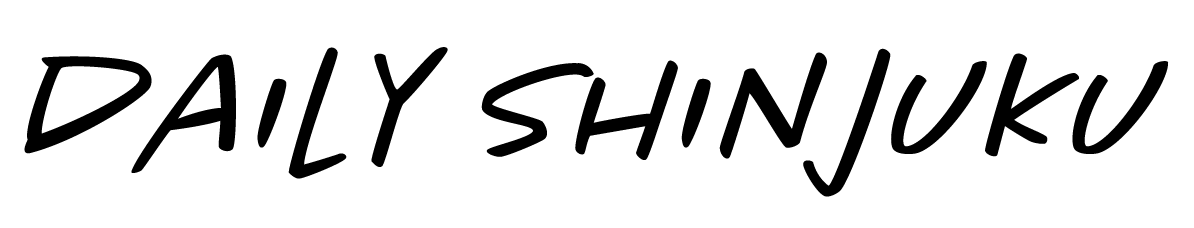近年、犬や猫といったペットとの外出スタイルが大きく変化している。都市部では高齢犬の増加や狭い歩道・階段の多さなど、従来の散歩スタイルだけでは対応しきれない課題も増えてきた。その一方で、スリングやキャリー、折りたたみ可能なペットカートなど、軽量で扱いやすいモビリティ製品が次々と登場し、飼い主の選択肢を広げている。
本記事では、ペットとの快適な外出を支える最新の移動補助具の特徴や、用途に応じた使い分け、そして市場・ブランド動向までを整理し、都市生活者にとっての“新しい外出スタイル”をわかりやすく紹介する。
犬と暮らす人の“外出スタイル”がここ数年で変化している理由
ここ数年、犬と暮らす家庭の外出スタイルが目に見えて変わってきた――その背景には「飼育頭数の構造変化」「ペットの高齢化」「都市生活の制約」が三つの大きな要因として絡み合っている。

まず飼育頭数は長期的に見ると減少傾向にある一方で、近年は減少幅が縮まりつつあり(総飼育頭数は2024年におよそ679.6万頭と推計される)、“飼う人の数”と“迎え入れられる頭数”のバランスが変化していることが分かる。
同時に犬の高齢化が進んでいる点も重要だ。栄養管理や獣医医療の進歩で平均寿命は延び、7歳以上を「高齢」とみなすとその割合は半数を超えるという調査結果もあり、老犬ケアや移動の負担軽減が飼い主の関心事になっている。介護的なケアや短時間で済ませたい外出ニーズが増えたため、抱っこや長時間の歩行が難しい犬のための代替手段の需要が高まっている。
さらに都市部での生活様式の変化──狭い歩道、階段やエレベーターの混雑、電車や商業施設での移動──が「外出のやり方」を変えている。都心での多頭飼いや外出先での“疲れ・階段・混雑”といった具体的な悩みが増えたことで、手ぶらで移動できるグッズや段差対策、公共スペースでのマナー配慮がセットで語られるようになった。実際、都市部でのペットカート普及を伝える報道も増えており、利便性を優先する傾向が可視化されている。
まとめると、数字で示される「頭数」の変化だけでなく、ペットの年齢構成と都市生活の制約が相互に作用して、外出の「選び方」「持ち物」「時間の使い方」が変わってきている――というのが現在の潮流だ。データに基づく傾向を押さえつつ、老犬ケアや都市移動での実用性を重視した情報提供が求められている。
広がるペット用モビリティ市場:スリング、キャリー、ペットカートの需要増加
近年、ペット――特に犬や猫――の移動補助具やモビリティ用品の市場が世界的に拡大を見せており、それは「飼い主のライフスタイルの変化」「高齢ペットの増加」「都市での暮らしの制約」といった社会背景と強く結びついている。
以下のような動きが見られる。

都市生活者のニーズと「実用モビリティ」
スリング、キャリー、ペットカートの需要増加を支えているのは、都市生活者のライフスタイルやペットとの関係性の変化である。
都市部では歩道が狭かったり、階段・エレベーター・混雑する公共交通を使うことが多く、「長時間の散歩」や「犬を歩かせること」が難しい場面が多くなっている。そうした状況では、軽量で折りたたみ可能なキャリーやペットカートが重宝される。
また、前段で触れたようにペットの高齢化も進んでおり、関節が弱くなった犬や老犬を無理なく連れて歩くには、抱っこや歩行だけでは負担が大きい。そうした飼い主とペットの「老犬ケア」「移動の負担軽減」のニーズを満たすのがモビリティ用品だ。
さらに、室内飼育が多く “散歩=外出” になる場合が多いため、キャリーやスリングを使うことで「荷物のように持ち運べる」「迷惑をかけにくい」「人混みにも対応しやすい」といった実用性が評価されている。
このように、都市生活 × 高齢ペット × 飼い主の利便性志向が、ペット用モビリティ市場の拡大を後押ししている。
SNS・コミュニティで話題になる製品カテゴリ
近年は、こうしたモビリティ用品が単なる“便利アイテム”を超えて、飼い主のライフスタイルの一部としてSNSやコミュニティで広がっていることも特徴的だ。
軽量でデザイン性の高いキャリーや「コンパクト折りたたみストローラー」は、都市での外出シーンに映え、写真映えや“オシャレペットライフ”的な価値があるとしてSNSで紹介されやすい。
また、老犬や体の弱いペットをケアする専用カート/車椅子は、「安心」「ケア重視」の飼い主コミュニティで情報交換されやすく、口コミで広がる傾向にある。特に多頭飼いや大型犬との外出を快適にする“ダブル用ストローラー”などは、ニッチながら注目が集まっている。
さらに、オンラインショップや専門ショップだけでなく、ペットイベント、ペット連れOKのカフェや施設の増加も、こうしたモビリティ用品の「当たり前化」を後押ししている。
こうした流れにより、「ペット用スリングやキャリー」「ペットカート」は単なる“補助器具”から、「ペットとの外出スタイルそのもの」を支える重要アイテムへと進化している。
用途ごとの最適な選択肢:スリング/リュック/キャリー/ペットカートの使い分け
犬との外出スタイルが多様化した今、「どの場面でどのアイテムを使うべきか」という視点が、飼い主の関心ごとになっている。スリング、リュック、キャリー、ペットカートといった移動用アイテムは、それぞれが異なる特徴を持ち、シーンによって“最適解”が変わってくる。

短距離向けのスリング
スリングは、最も“短距離向け”のモビリティだ。抱っこの延長で使える手軽さが最大の特徴で、体重3〜5kg程度の小型犬との相性が良い。
近所の散歩中に「ちょっと抱っこしたい」ときや、動物病院までの短距離移動など、“素早く出して、素早くしまえる”場面で便利。
布製で軽量なため、荷物としてかさばらず、カフェの入店時や人混みで犬を保護したいときにも適している。ただし、長時間の移動には向かず、飼い主の肩に負担がかかりやすい点は注意したい。
旅行・アウトドアで人気の犬用リュック
近年人気が高まっているのが犬用リュック。両手が完全に空くため、「旅行」「アウトドア」「電車移動」など、アクティブな外出との相性がよい。
背面で体重を支えるため、スリングよりも重めの犬(5〜8kg前後)にも対応しやすく、ハイキングや街歩きでも安定感を保てる点が評価されている。
また、前面開閉・通気性・クッション性といった要素が進化し、飼い主・犬双方の負担軽減が進んでいるのも特徴。
ただし長時間入れっぱなしにすると犬の体勢が崩れやすいため、途中でこまめに外へ出して休ませることが前提となる。
安定性重視のキャリーケース
キャリーケースは、安定性と安全性を最優先する場面で強い。
電車・バス・新幹線といった公共交通機関の利用、あるいは飛行機を使った国内移動では、揺れを抑え密閉性を確保できるキャリーが基本となる。
- 騒音や振動から犬を守る
- しっかりしたフレームで“倒れにくい”
- 長時間でも体勢を保ちやすい
といったメリットがあり、旅行や移動距離の長い外出では欠かせない存在だ。
一方で、重量があり手持ちだけでは疲れやすいため、キャスター付きモデルやキャリー+カートの“二刀流”を選ぶ飼い主も増えている。
長時間の外出や高齢犬向けのペットカート
ペットカートは、長時間の外出・人混み・高齢犬ケアの三軸で活躍する、最も汎用性の高いモビリティだ。
特に次のような場面で強みを発揮する:
- ショッピングモール・アウトレットなど“歩く距離が長い”外出
- 旅行先での長距離移動
- 足腰の弱いシニア犬、術後・持病のある犬との外出
- 体重が重く、抱っこやリュックが難しい犬(6kg以上が目安)
犬の負担が圧倒的に小さく、飼い主の腕や腰に負担をかけないため、外出の選択肢そのものを広げるアイテムとして存在感が増している。
内部の居住性や振動吸収など“快適性”を重視するモデルが増えたことで、近年は若い犬との普段使いで選ぶ人も増加している。
飼い主が求める“軽さ・安全性・利便性”:最新カートで進む改善点
ペットとの外出スタイルが多様化した今、ユーザーが重視する基準も明確になってきた。近年のトレンドとして浮上しているのが「軽さ」「安全性」「利便性」の3軸だ。各ブランドはこの3点を中心に改良を進め、都市生活にも適した“持ち運べるモビリティ”として進化を続けている。

軽量化技術――“押す負担”と“持ち運びストレス”の低減が加速
都市部では階段移動・乗り換え・商業施設の昇降など、カートを“持ち上げる場面”が意外と多い。
そのため、近年の新モデルではアルミフレームや軽量樹脂パーツを採用し、総重量を抑える方向が主流となっている。
特に多頭飼いや中型犬サイズでは“1kgの重さの差が体感ストレスを大きく左右する”と語るユーザーも多く、軽量化は製品選びの中心条件として定着しつつある。
ワンタッチ収納の進化――折り畳みの手間削減が競争力に
もうひとつ注目されているのが、折り畳み機構のアップデートだ。
従来のペット用キャリーコットは、
- サポートバーの取り外し
- 旋回形式の折り畳み
- 本体を大きく持ち上げて動かす必要がある
といった“二手三手”の作業が必要で、使い勝手に課題が残っていた。
それに対し、最近はワンタッチで折り畳める“時短技術”が主流になり、
階段前や電車の改札前など“素早く畳みたい瞬間”での利便性が評価されている。
安全性――タイヤ・ベルト・フレームの強化が進む
ユーザーの声を背景に、各ブランドは安全要素の強化も加速している。
- ダブルホイールや衝撃吸収タイヤで段差・石畳対策
- 5点式シートベルトや飛び出し防止リードの標準化
- フレーム・コット底板のねじれ耐性の改善
といったアップデートが増え、「ペットの揺れを抑えたい」「電車の揺れが心配」といったニーズにも対応するようになった。
デザインの進化――都市生活者の“持ちたい”を意識
従来は機能重視のラインナップが多かったが、近年は“普段持ちでも違和感のないデザイン”が増加している。
ミニマルなカラー、レザー調ハンドル、インテリアに馴染む素材など、“ファッションアイテム化”が進んでいるのも特徴的だ。
SNSでの見せ方を意識したモデル、写真映えを重視した配色など、外出の様子をシェアする文化も設計に反映されつつある。
ペットとの快適な外出を支える企業の取り組み

ペットとの外出需要が年々高まるなか、各ブランドは「快適性」「安全性」「軽量化」の3点を軸にした技術開発を加速させている。近年は、ベビーカー領域で培われた構造技術を応用し、折り畳み動作の簡略化や車体の剛性向上に取り組む企業が増えている。
特に注目されるのが、新しい折り畳み構造の採用だ。従来は複数ステップを踏む必要があったモデルが一般的だったが、片手で素早く畳めるワンタッチ式や、フレームの可動域を最適化して動作を大幅に簡略化する仕組みが広がりつつある。
こうしたユーザーの「軽さ・利便性」への要求に応えるため、各社は折り畳み機構の改良を進めており、例えばPETTENAが採用する「X-fold」構造は、片手操作で素早く畳めることから、駅の階段や急な段差が多い都市部の利用者から支持を集めています。
また、安全基準の強化も進む。欧州のベビーカー規格 EN1888に準拠した製品のように、走行・耐荷重・ブレーキなど複数の項目で高い水準を満たすモデルが増え、長時間利用でも安定性を保てる設計が主流になりつつある。
さらに、飼い主の声を反映した改善も活発だ。直近では「階段の多い駅でも運びやすい軽量モデル」「電車での乗り降りを想定した静音タイヤ」「キャリーの取り外しやすさ」など、都市生活者の利用シーンに合わせたブラッシュアップが進んでいる。国内外ブランドともに、これまでの“重くて扱いづらい”イメージを払拭し、よりモビリティ性の高いラインナップを揃え始めた。
こうした技術の進化により、ペットとの外出は「特別なイベント」から「日常の移動手段」へと変化しており、業界全体が新たなステージに移行しつつある。
まとめ
ペットとの外出需要が拡大するなか、移動時の負担を減らすための「軽さ・安全性・快適性」はこれまで以上に重視されるようになっている。キャリーバッグやスリングなど選択肢が増える一方で、折りたたみペットカートは“より楽に、より安全に”移動できる手段として存在感を高めている。
今後も技術革新が進むことで、都市生活にもアウトドアにも適した、新しいペットモビリティが登場していくことが期待される。